What We Do

社会デザイン実践のための知を伝える
Book
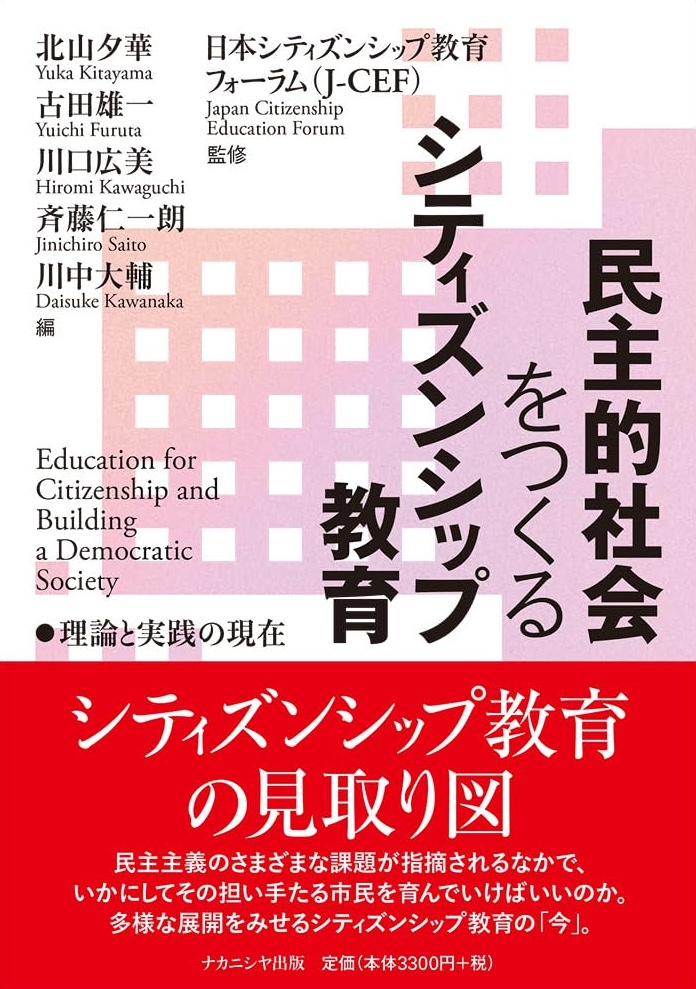 『民主的社会をつくるシティズンシップ教育』
『民主的社会をつくるシティズンシップ教育』
民主主義のさまざまな課題が指摘されるなかで、いかにしてその担い手たる市民を育んでいけばいいのか。多様な展開をみせるシティズンシップ教育のの見取り図を提供する。
日本シティズンシップ教育フォーラム(J-CEF)監修/北山夕華・古田雄一・川口広美・斉藤仁一朗・川中大輔編(担当:共編者, 範囲:「民主主義とシティズンシップ教育の現在地から」pp.1-12.)
ナカニシヤ出版 2025年7月
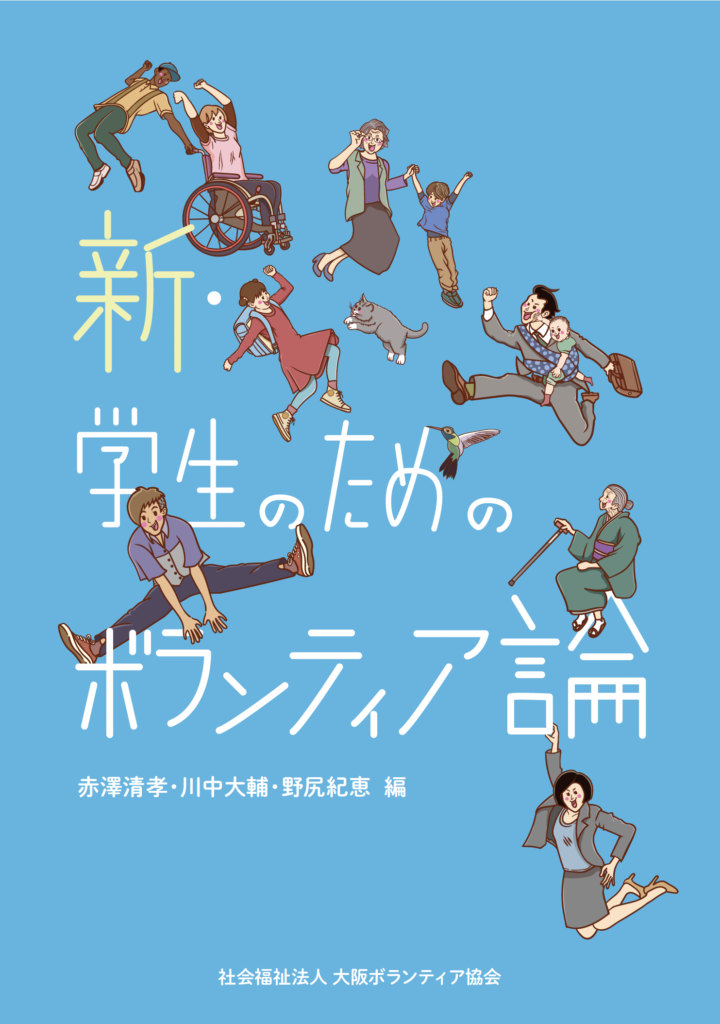 『新・学生のためのボランティア論』
『新・学生のためのボランティア論』
2006年に刊行され、ロングセラーを続けていた『学生のためのボランティア論』(岡本榮一・菅井直也・妻鹿ふみ子編)を約20年ぶりに全面改訂したものである。言葉は知っているけれど、掘り下げていくと説明することが難しい「ボランティア」や「ボランティア活動」について、さまざまな視点から考察し、その本質や可能性に迫っている。
赤澤清孝・川中大輔・野尻紀恵編 (担当:共編著, 範囲:「ボランティアと社会デザイン–私たちはどういう社会を目指すのか」pp.176-182,「SDGsとボランティア」pp.44-47,「刊行にあたって」pp.2-3.)
大阪ボランティア協会 2025年1月
 『社会デザインをひらく』
『社会デザインをひらく』
社会デザインとは何なのか。本書では、日々思索を重ねてたどりついたその有りようがしたためられ、いっぽうでは実践のかたわら得られた教訓が語られる。わたしたちは多種多様な社会デザインの地平に立ちながらも、今後いかにして住みやすい社会をつくればいいのだろう。その重要なヒントをこの本からくみ取ってほしい。
中村陽一監修/志塚昌紀・川中大輔・菅井薫・川田虎男編著 (担当:共編著, 範囲:「社会的排除に抗うコミュニティ・デザイン–居場所とエンパワメント」pp.32-49,「多文化共生と市民教育–社会意識と自己認識の脱植民地化に向けて」pp.88-105,「おわりに」pp.235-236.)
ミネルヴァ書房 2024年11月
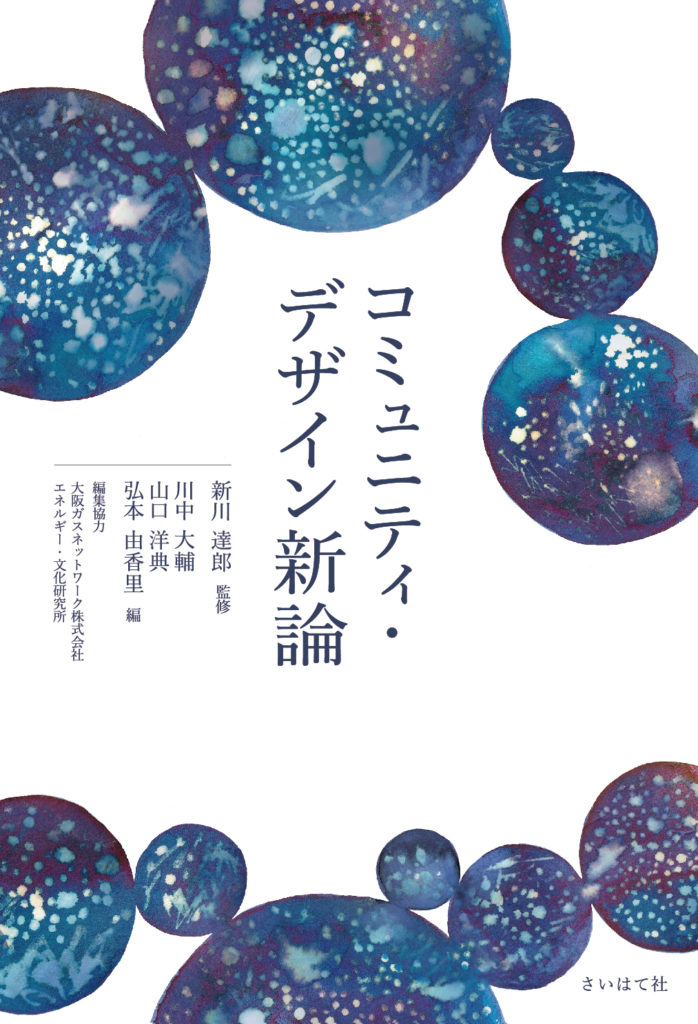 『コミュニティ・デザイン新論』
『コミュニティ・デザイン新論』
現代社会の困難=希望をめぐる難問に挑む——政策科学、社会学、減災・人間科学、建築・都市計画学、 事業構想学など、バックグラウンドの異なる気鋭の執筆陣が集い、旧来のコミュニティ・デザイン論を捉え直し、アクティブな知として新たに鍛え直すことを目指す。(第23回日本NPO学会賞優秀賞受賞)
新川達郎監修/川中大輔・山口洋典・弘本由香里編 (担当:共編著, 範囲:「共生社会を先導する市民性とは?」pp.60-90, 「対談–難問に向き合っていくために」pp.18-41,「あとがき」pp.343-349.)
さいはて社 2024年9月
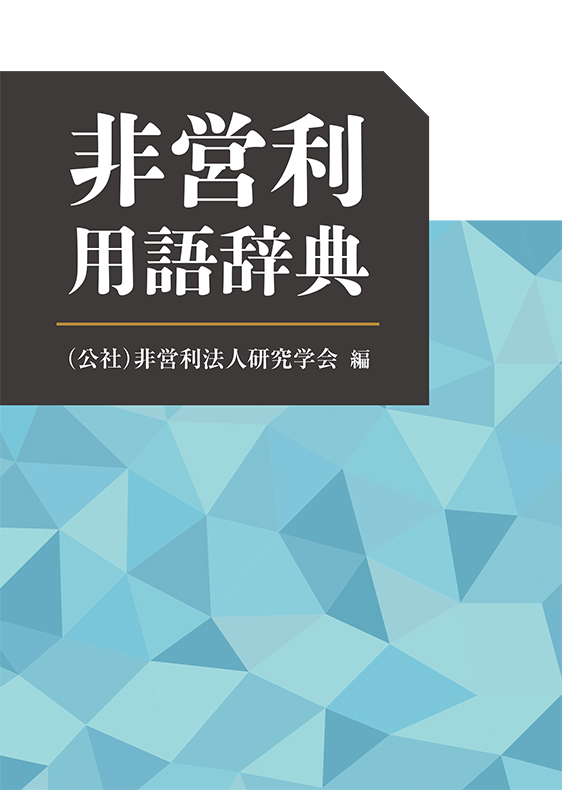
『非営利用語辞典』
非営利の領域で特殊に使う専門用語にかぎり、重要度の高い用語904語を収録。「学究の用いる基本的な諸概念や諸理論」の簡潔な解明、「非営利に固有な制度・機関・法制」の解説も加える。
(公社)非営利法人研究学会編 (担当:項目執筆,範囲:「シティズンシップ教育」pp.172-173,「市民権」p.180.)
全国公益法人協会 2022年3月
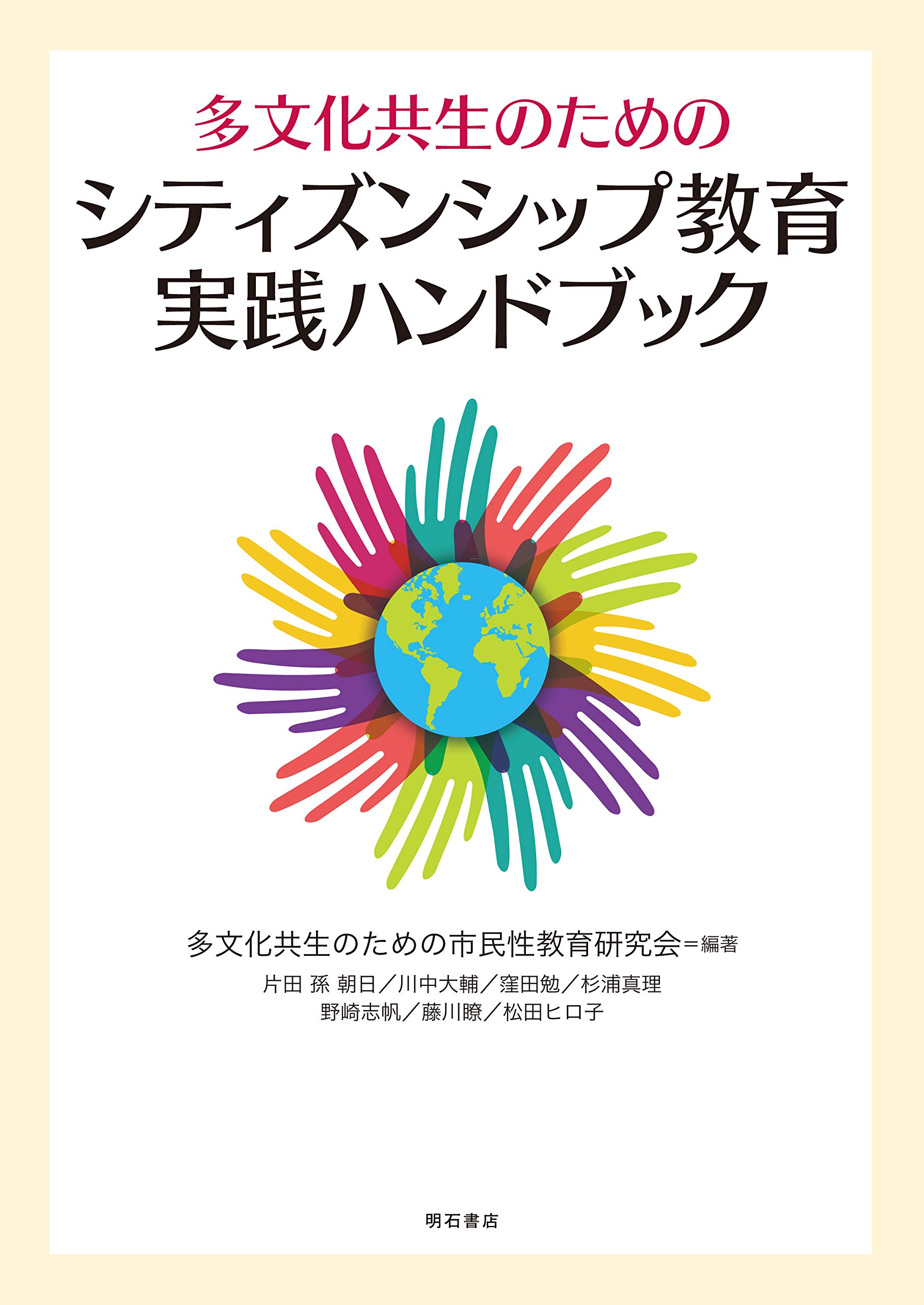 『多文化共生のためのシティズンシップ教育実践ハンドブック』
『多文化共生のためのシティズンシップ教育実践ハンドブック』
シティズンシップ教育の授業づくりと実践に活用できる教材集。多文化、多様性、社会的包摂、アイデンティティなどの観点から、学校のルールづくり、住居、労働、医療、災害など7つのテーマを設定し、学習者に「主権者とは誰か?」を問いかける授業を提案する。
多文化共生のための市民性教育研究会編著(担当:共編著,範囲:「避難所で考えよう:合意形成と多数決」pp.112-129,「民主主義と多数決」p.130,「メディア・リテラシーの必要性と現代的課題」p.85,「パフォーマンス評価とルーブリック」pp.17-23.)
明石書店 2020年3月
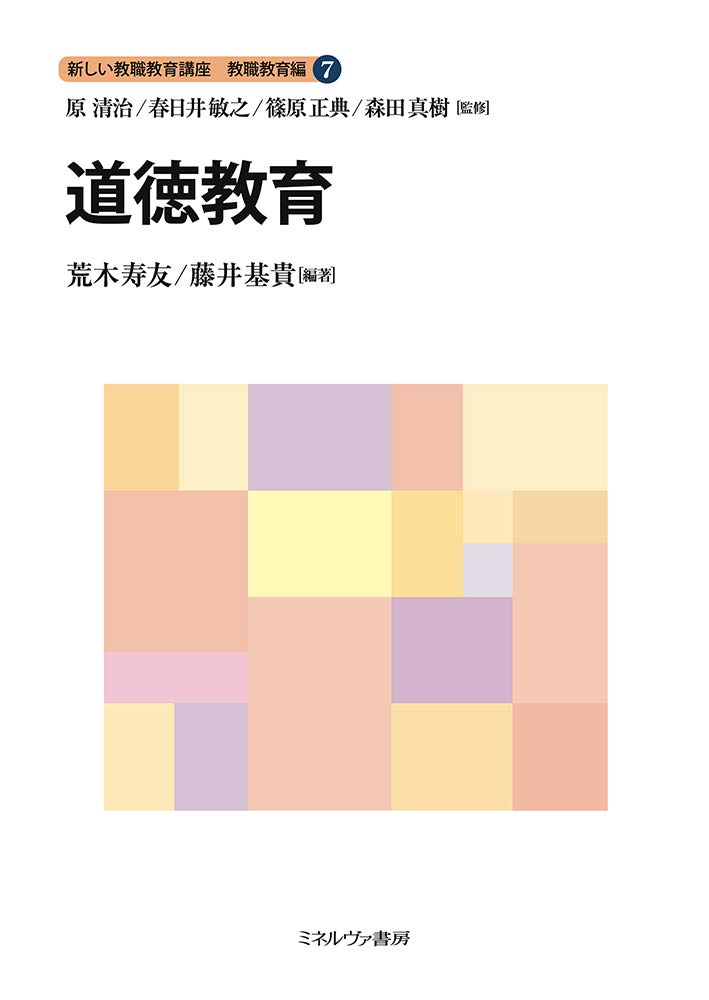 『道徳教育』
『道徳教育』
コアカリキュラムに定められた目標に則り,すぐにでも授業を組立てて実施できるよう構成。「特別の教科 道徳」実施以降の課題やこれまでの道徳教育の内容とその歴史,子どもの問題,評価など13章に分けて詳しく解説していく。
荒木寿友・藤井基貴編著(担当:分担執筆, 範囲:「シティズンシップ教育と道徳教育」pp.174-194.)
ミネルヴァ書房 2019年5月
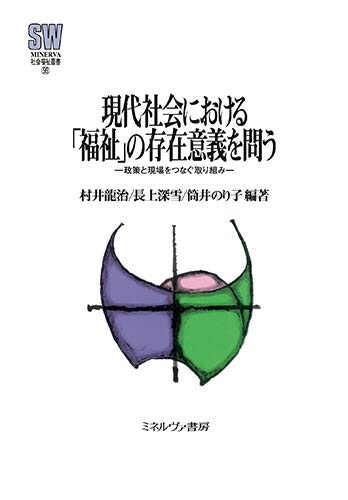
『現代社会における「福祉」の存在意義を問う』
人口減少、貧困/格差の拡大等、現在の日本社会には、大きな課題が多数存在している。その背景や構造を明らかにした上で、制度統合、多職種連携、市民参画等を事例に、「社会福祉政策」と「福祉現場」が乖離している現状を分析した。そして、その乖離を解消するための方策と、現代社会において求められる「福祉」について考察した。
村井龍治・長上深雪・筒井のり子編著(担当:分担執筆, 範囲:「『市民による社会貢献』と社会的企業–自発的社会福祉の先駆性の発揮に向けて」pp.106-130.)
ミネルヴァ書房 2018年11月
 『シティズンシップ教育で創る学校の未来』
『シティズンシップ教育で創る学校の未来』
本当の意味での「民主主義」とは、一体何だろう――。 選挙離れや震災以降の防災等の課題の中で、シティズンシップ教育が改めて注目されている。社会の出来事を自分事として捉える若者を育む“学校の未来”を創るため、総勢27名が理論と実践をもち寄った。
唐木清志・岡田泰孝・杉浦真理・川中大輔監修/日本シティズンシップ教育フォーラム編(担当:共編著, 範囲:「社会で展開されるシティズンシップ教育」pp.32-39.及び全体監修)
東洋館出版社 2015年3月
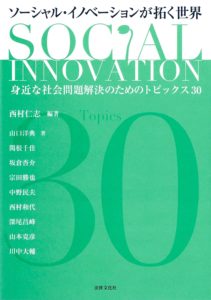 『ソーシャル・イノベーションが拓く世界』
『ソーシャル・イノベーションが拓く世界』
社会における様々な「困りごと」解決のための方法論と実践例を提示。トピックごとにどこからでも読み始め/読み切ることができるコンパクトなつくりで、実践や研究への第一歩をサポート。
西村仁志編(担当:分担執筆, 範囲:「生と死」pp.88-94.)
法律文化社 2014年10月
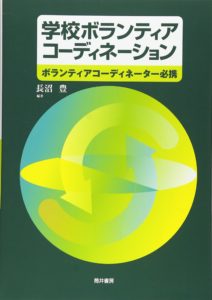 『学校ボランティアコーディネーション』
『学校ボランティアコーディネーション』
経験年数の少ないコーディネーターにも理解できるよう、ボランティア活動・学習、学校教育に関する基礎的・基本的な項目を紹介し、学校ボランティアコーディネーションを具体的な事例とともにさまざまな角度から解説する。
長沼豊編(担当:分担執筆, 範囲:「アイスブレイクとその技法」pp.172-188.)
筒井書房 2009年6月
Paper
シティズンシップ教育・若者/市民の社会参加
-
- 子ども・若者研究への/からの接続に向けて(2025年)
(子ども・若者参画研究会『こわかけんマガジン』2025年11月号) - 変化に開かれた「わたし」への気づき(2025年)
(滋賀県保護司会連合会『更生保護びわこ』133号) - 子ども・若者参画の場をどうひろげるか–こども家庭庁『こども若者★いけんぷらす』のゆくえを考える(2025年)
(日本子どもを守る会編『子ども白書 2025』かもがわ出版) - ソーシャル・イノベーション実践の巨大化・高度化・民主化(2024年)
(日本ソーシャル・イノベーション学会『ソーシャル・イノベーション研究』3号) - キャンプにおける子ども・若者参画の実践と課題(2024年)
(日本キャンプ協会『CAMPING』209号) - 違いを認めながら納得解を導き出す 多文化共生社会に必要な創造力(2024年)
(先端教育機構『月刊先端教育』2024年5月号) - 幸せになる生き方の陥穽(2024年)
(放送大学滋賀学習センター『樹滴』131号) - ほどけた社会的絆を結び直す(2024年)
(滋賀県保護司会連合会『更生保護びわこ』130号) - 成長に焦点,市民社会の担い手を育もう(2023年)
(大阪ボランティア協会『ウォロ』551号) - 多文化共生のための批判的実践に向けて(2023年)
(大阪ガスネットワーク(株)エネルギー・文化研究所「実践哲学としての『コミュニティ・デザイン論研究』を目指して」ワーキング・ドキュメント) - 生命感のあふれる遊び(2023年)
(放送大学滋賀学習センター『樹滴』126号) - 自発性を起点に据えないボランティアコーディネーション(2022年)
(日本ボランティアコーディネーター協会『Co☆Co☆Net』第66号) - 「共にいる」社会から「共に生きる」社会へ(2021年)
(八幡市『広報やわた』2021年12月号) - 特権への自覚/人権への覚醒(2021年)
(放送大学滋賀学習センター『樹滴』119号) - 官の「行き過ぎたスリム化」をどう立て直すか?(2020年)
(神戸まちづくり研究所『まち研便り』第3号) - 地域と大学のより高次な連携に向けて(2020年)
(龍谷大学社会学部『2019年度 大津エンパワねっと活動報告書』) - 絶望と希望の間に。(2020年)
(放送大学滋賀学習センター『樹滴』114号) - コミュニティ・デザイン新論–「排除か包摂か」を越えて(2019年)
(大阪ガス(株)エネルギー・文化研究所『CEL』2019年11月号) - 社会参加に距離をとる若者とどう向き合うか(2019年)
(『部落解放』779号,解放出版社) - 低きに立つ「コミュニティ・デザイン」
−-社会的排除に立ち向かう戦略をどう描いていくか?(2017年)
(大阪ガス(株)エネルギー・文化研究所『2017年度「コミュニティ・デザイン論研究」レクチャー・ドキュメント』) - 「公共の市民化」としての協働へ(2017年)
( 神戸市協働と参画のプラットホーム『協働コーディネーターマニュアル』) - 社会のオーナー意識が育つシチズンシップ教育(2016年)
( 学研『進学情報』2016年8月号 ) - 学びを深める「ふりかえり」(2016年)
(日本フィランソロピー協会『チャリティー・チャレンジ・プログラムハンドブック』) - 社会創造に参加する市民はいかにして育つか?
–「社会」と「学び」からコミュニティ・デザインを考える(2016年)
(大阪ガス(株)エネルギー・文化研究所『「コミュニティ・デザイン論研究」読本』) - 「市民」になるための意識と行動を育み、思いをカタチにしませんか(2016年)
(コープともしびボランティア振興財団『ともしび通信』86号) - 市民社会の担い手を育てるのは誰か?(2016年)
(大阪ボランティア協会『ウォロ』507号) - 若者の思いがカタチになる地域へ(2015年)
(NPO法人わかもののまち「講演録」) - 考える市民を育てる(3回掲載)(2015年)
(「日本教育新聞」 2015年9月28日−10月12日) - 市民は弱い。だから市民は「共に」社会を変える。(2015年)
(公職研『地方自治職員研修』 2015年12月号) - 若者が政治への信頼を育む機会はどれだけあるのか?(2015年)
(京都市ユースサービス協会『ユースサービス』22号) - 冒険的なサービスラーニングへ (2014年)
(立命館大学サービスラーニングセンター「リレーコラム」, サイトはこちら) - 「市民の歴史」を編む(2013年)
(日本シティズンシップ教育フォーラム『J-CEF NEWS』vol.1) - 市民としての意識と行動力を育む学びの場をつくる(2013年)
(『月刊 生涯教育』2013年4月号) - よい主権者になる学び−シティズンシップ教育の基礎と実践−(2012年)
(明るい選挙推進協会『シティズンシップ教育』) - 若者に「復興の誇り」を育もう(2011年)
(「石巻日日新聞」2011年11月12日) - 21世紀社会における若者の変容(2009年)
(文科省委託調査『小中学生を対象とした通年型冒険教育プログラムにおける青年リーダーへの効果検証』所収) - 学校における「市民的リテラシー教育」導入の方向性
-教育を通じた公共圏のコミュニケーションの成熟化に関する一考察(2005年)
(立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科提出修士論文) - 地域課題を解決する体験から学ぶ(2005年)
(『社会科教育』2005年1月号,明治図書) - 「居心地」を悪くする快楽-日常のなかのカルチュラル・スタディーズ実践(2004年)
(A SEED JAPAN『種まき』88号) - 「パブリックなこと」をひらくメディア・リテラシー
-公共圏を通じた社会変革のアプローチに関する一考察(2003年)
(関西学院大学社会学部提出卒業論文)
NPOマネジメント
-
- 「覚悟を決めるために,企画書をつくる!」(2011年)
(佐々倉玲於ファシリテーター事務所編『いなかビジネス教えちゃる!カツオ指南本』所収) - 「第1回 マンネリ化への気づき」(「家の光ニュース」以下同じ,2010年7月号)
- 「第2回 つながる幸せのおすそ分け」(2010年8月号)
- 「第3回 外を探すまえに内にある力を活かす」(2010年9月号)
- 「第4回 会議への懐疑をほぐす」(2010年10月号)
- 「第5回 参加者みんなが支える会議」(2010年11月号)
- 「第6回 参加者みんなが支える会議(2)」(2010年12月号)
- 「第7回 脱ひらめきの企画づくり」(2011年2月号)
- 「第8回 思いをカタチにする方法」(2011年3月号)
- 「第9回 気持ちがつながる広報へ」(2011年4月号)
- 「第10回 参加で共につくる広報へ」(2011年5月号)
- 「第11回 マンネリ化を予防する評価」(2011年6月号)
- 「第12回 今こそ、変化への勇気と行動を!」(2011年7月号)
- 「覚悟を決めるために,企画書をつくる!」(2011年)
Class
担当科目(2025年度)
-
-
- 関西学院大学 人間福祉学部「ボランティア論」
- 関西学院大学 人間福祉学部「社会起業入門」
- 関西学院大学 人間福祉学部「社会起業プラクティス演習」
- 関西学院大学 人間福祉学部「社会起業プラクティス」
- 関西学院大学 人間福祉学部「社会起業アドバンスト・インターンシップ」
- 関西学院大学 人間福祉学部「Pracitice Skill Set」
- 関西学院大学 人間福祉学部「基礎演習」
- 関西学院大学 人間福祉学部「社会起業入門演習」
- 関西学院大学 人間福祉学部「研究演習Ⅰ」
- 龍谷大学 社会学部「社会イノベーション実践論」
- 龍谷大学 社会学部「現代福祉学演習ⅡA・ⅡB」
- 龍谷大学 社会学部「卒業研究」
過去の担当科目
-
- 龍谷大学 社会学部「社会貢献論」
- 龍谷大学 社会学部「社会企業論」
- 龍谷大学 社会学部「コミュニティデザイン」
- 龍谷大学 社会学部「社会共生実習ⅠA・ⅠB, ⅡA・ⅡB,ⅢA・ⅢB」
- 龍谷大学 社会学部「社会教育実習」
- 龍谷大学 社会学部「基礎ゼミナールA・B」
- 龍谷大学 社会学部「現代福祉学演習ⅠA・ⅠB」
- 龍谷大学 社会学部「現代福祉学演習ⅡA・ⅡB」
- 龍谷大学 社会学部「卒業研究」
- 龍谷大学 農学部「社会福祉論」
- 龍谷大学 教養教育センター「ボランティア・NPO入門」
- 龍谷大学 教養教育センター「キャリア入門」
- 立命館大学 政策科学部「社会的企業論」
- 立命館大学 共通教育推進機構「地域参加学習入門」
- 立命館大学 共通教育推進機構「現代社会のフィールドワーク」
- 立命館大学 共通教育推進機構「シチズンシップ・スタディーズⅠ・Ⅱ」
- 立命館大学 共通教育推進機構「ソーシャルコラボレーション演習」
- 立命館大学 共通教育推進機構「教養ゼミナール」
- 立命館大学 共通教育推進機構「ボランティア活動支援演習」
- 立命館大学 共通教育推進機構「ボランティアマネジメント論」
- 立命館大学 共通教育推進機構「ボランティアインターンシップ」
- 立命館大学 共通教育推進機構「ボランティア情報・調査演習」
- 立命館大学 共通教育推進機構「社会とボランティア」
- 放送大学 教養学部「ソーシャル・イノベーション論」
- 放送大学 教養学部「ソーシャルビジネス論」
- 放送大学 教養学部「卒業研究指導」
- 放送大学 滋賀学習センター「社会デザイン研究セミナー」
- 放送大学 滋賀学習センター「ソーシャル・イノベーション研究セミナー」
- 放送大学 滋賀学習センター「コミュニティ・デザイン研究セミナー」
- 放送大学 滋賀学習センター「ボランティア研究セミナー」
- 同志社大学大学院 総合政策科学研究科「コミュニティ・デザイン論研究」
- 甲南大学 マネジメント創造学部「NPO(公共経営の先端Ⅰ)」
- 甲南大学 共通教育センター「ボランティア論」
- 甲南女子大学 文学部「社会起業論Ⅰ・Ⅱ」
- 甲南女子大学 文学部「NGO/NPO論」
- 甲南女子大学 文学部「NGO論B」
- 甲南女子大学 文学部「組織マネージメント入門」
- 甲南女子大学 文学部「ボランティア入門」
- 大阪経済大学大学院 人間科学研究科「人間共生特殊講義」
- 大阪成蹊大学大学院 教育学研究科「シティズンシップ教育特論」
- 大阪成蹊大学芸術学部「キャリアプランニング論」
- 大阪樟蔭女子大学大学院 人間科学研究科「非営利ビジネス論」
- 大阪樟蔭女子大学大学院 人間科学研究科「ボランティア活動論」
- 大阪樟蔭女子大学 学芸学部「教育社会学」
- 神戸国際大学 経済学部「市民参加論」
- 美作大学 生活科学部「ボランティア論[福祉系]」
- 上智大学 グリーフケア研究所「NPO論」
- 岐阜県立森林文化アカデミー「コミュニティ・デザイン論」
- 岐阜県立森林文化アカデミー「NPO概論」
- 国立明石工業高等専門学校「アクティブラーニング入門」
- 関西労災看護専門学校「教育学」
- 日本デザイナー学院「NPO・コミュニケーション概論」
- 日本デザイナー学院「パブリックデザインワーク」
- *大学での授業内容をもとに,その一部または全部を集中講義形式で学ぶ場を担当することも可能です。ご関心ある方は,ご相談ください。
-
- 子ども・若者研究への/からの接続に向けて(2025年)



